�@
|
|
�T�@��Ɖ��l�Ƃ�
�@��Ɖ��l�Ƃ�
��Ɖ��l�Ƃ́A��Ƃ��̂��̂̉��l��ݕ����l��ŕ\������ߒ��y�т��̌��ʂƂ��Ă̋��z���w���܂��B
�A��Ɖ��l�����ڂ���Ă����w�i
�@���{�̎������B�͂��Ď�������Ƃ����Ԑڋ��Z���嗬�ł����B�������ߔN�A��Ƃ̍����o���S�ەs����A�������e������������Ԑڋ��Z���݂͌�������A��Ƃ͒��ڋ��Z�ɂ�鎑�����B�𑣐i���n�߂܂����BM&A�̊������������āA�Ԑڋ��Z���璼�ڋ��Z�ւ̃V�t�g�������A�����Ƃ���ғ��̃X�e�[�N�z���_�[��Љ�I�ӔC���d�������o�c�A���Ȃ킿��Ɖ��l�o�c���r���𗁂тĂ��܂����B
�@��Ɖ��l���ӎ������o�c�����ڂ���Ă����킯�ł�����A�u������Ɖ��l���v�A�u�ǂ�����Ί�Ɖ��l�͏オ�邩�v�Ƃ������Ƃ����ڂ���܂��B��Ɖ��l�]�����@�͗l�X����܂����A��Ƃ������̂͂Ȃ��A�ǂ̎�@�������b�g������f�����b�g������܂��B
�U�@DCF�@
�@��������́A��Ɖ��l�]�����@�̂ЂƂł��茻�݂̃g�����h�ŁAValue Express�Ŏg�p���Ă���DCF�@�ɂ��Ă̐����ł��B
�@DCF�@���䓪���Ă����w�i
��Ɖ��l�]�����@�ɂ͗l�X�Ȃ��̂�����܂����A�����̎w�W���A�ߋ��̌��ʂ��ړx�ɒu���Ă���Ƃ������_���w�E����Ă��܂����B��Ƃ̓S�[�C���O�R���T�[���Ƃ��ď����Ɍ������Đi��ł������̂ł���A���������������w�W���K�v�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���オ�L�тĂ��Ă������J��ɍs���l�܂��������|�Y��A�̎Z���̈����A�ɁE�ݔ��ߏ蓙�̌����ɂ��A��Ɖ��l�̒ቺ���A���̂����Ƃ͑�������܂��B�ߔN���Z�@�ւ��A��Ƃ̐��ݏo���L���b�V���t���[�������ۂ̔��f�ޗ��̂ЂƂƂ���P�[�X���������Ă��܂��B���̂悤�Ȓ��A�K�R�I�ɏ����̃L���b�V���t���[�����Ƃ����]�����@�����ڂ���Ă��܂����B���ꂪ�A�������ݏo�����v�A�t���[�L���b�V���t���[�i�ȉ�FCF�j�����݉��l�Ɋ���߂������̂���Ɖ��l�ƍl������@�A���Ȃ킿DCF�@�i�����L���b�V���t���[�@�j�ł��B
�ADCF�@�̃����b�g�A�f�����b�g
�@DCF�@�̃����b�g
�E �ߋ������łȂ��������������Ă���
�E �ǂ̂悤�ȃr�W�l�X�v��������Ɖ��l�����コ���邩��������₷��
�E ��v��̔���◘�v���ƈႢ�A�L���b�V���t���[�Ƃ������܂����ɂ����w�W���g�p���Ă���
�E �u�Ώۊ�Ƃ̏��������߂̔��f�c�[���v�Ƃ����ړI�Ŏg�p�ł��邱�Ƃ���AM&A�ɂ����Ďg�p���₷��
�@DCF�@�̃f�����b�g
�E �����i�ŋ�������֎~���邽�߁A�Ŗ����ǂ����߂����@������j���Ƃ̐��Z�̏�ʓ��A�g�p�ɓK���Ȃ���ʂ�����BDCF�@�͖��\�ł͂Ȃ��A�����܂ŕ]�����@�̂ЂƂł���
�E �����v��̍����ɂ���ĉ��l���傫���ω�����
�E ��Ίz�ŕ\����邽�߂ɑ��ЂƂ̔�r�����ɂ���
�BDCF�@�ɂ��Z�o���@
�@DCF�@�ʼn��l���Z�o����ɂ́A��G�c�Ɍ����Q�i�K�̍�Ƃ�v���܂��B���i�K�Ƃ��ăt���[�L���b�V���t���[�i�ȉ�FCF�j���Z�o���A���i�K��FCF���������i���{�R�X�g�j�Ŋ������A��Ɖ��l���Z�o���܂��B
�@
�B-1 ���i�K�FFCF�̎Z�o
�@FCF���o�험�v�{�x�������|��旘���{�������p��|�ŋ��|�^�]���{�����z�|�ݔ������z
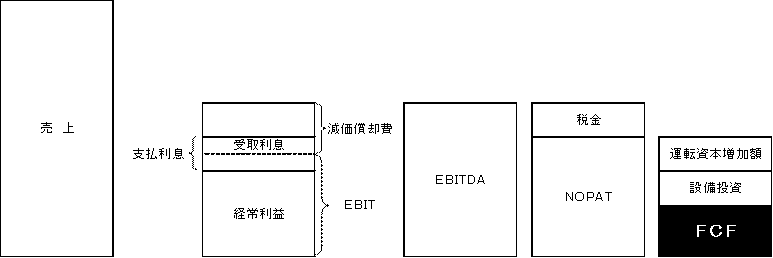 |
�EEBIT�F���������O���O���v
�EEBITDA�F���������O���O�������p�O���v
�ENOPAT�F�ň�����c�Ə����v
�EFCF�F�t���[�L���b�V���t���[�A���Ƃ̐��ݏo�����L���b�V���t���[�ŁA���҂⊔��ւ̊��Ҏ��v�̎x��������ƂȂ�
FCF�̎Z�o���@�͑O�}�̂Ƃ���ł��B���オ�����Ă����v�������Ȃ���L���b�V���C���͑������A�^�]���{��ݔ�������������A�L���b�V���A�E�g�������邽�߁A�L���b�V���C���͌����Ă��܂��܂��B�������ӂ��K�v�Ȃ̂́A�L���b�V���C���𑝂₷���߂Ɉ��Ղɉ^�]���{��ݔ����������点�悢�Ƃ����킯�ł͂���܂���B��Ƃ����Ƃ𑶑������邽�߂ɂ́A�^�]���{��ݔ������͕K�v�ł���A�������Ȃ����Ă��܂����Ƃ͊�Ƃ̑������̂�����ɂȂ�܂��B�������ߏ�ȉ^�]���{�̑�����ݔ������́A�L���b�V�����͊�����\��������܂��B�d�v�Ȃ̂͐g�̏�ɂ��������������邱�Ƃ�A�����Ɍ����������v���m�ۂ��邱�Ƃł��B
�B-2 ���i�K�FFCF�����Ɓi�����j���l�̎Z�o
�@FCF���Z�o�ł���Ύ��͑��i�K�ŁA�������N����FCF���������i���{�R�X�g�j�Ŋ������č��v�����Ɖ��l�����߂܂��B���Ɖ��l�����߂�ꂽ��A��c�Ɨp���Y�i�V�x�n�A�L���،����̋��Z���Y�j�����Z���Ċ�Ɖ��l�����߁A��Ɖ��l����L���q�����T�����Ċ������l�����߂܂��B
�@FCF�̌��݉��l���v�����Ɖ��l�i���Ƃ̐��ݏo�������l�j
�@���Ɖ��l�{��c�Ɨp���Y�i�V�x�n�A�L���،����̋��Z���Y�j����Ɖ��l�i��ƑS�̂̉��l�j
��Ɖ��l�|�L���q���i�ؓ����A�Ѝ��j���������l
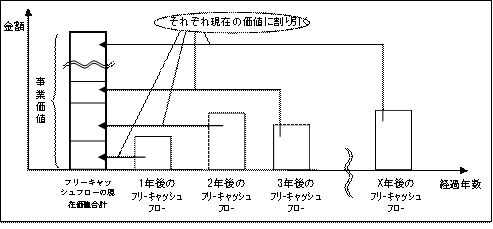 |
�P�@���Ɖ��l�i���Ƃ����ݏo�������l�j�́A�\�z�����e�N�x��FCF���������i���{�R�X�g�j�ɂ�茻�݂̉��l�Ɉ����Ȃ����A���Z�������̂ł��B
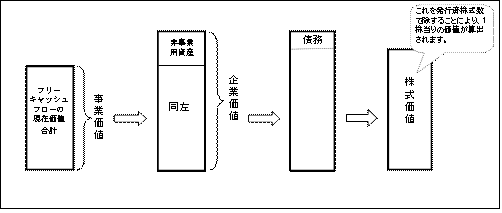 |
�Q�@��Ɖ��l�i��ƑS�̂̉��l�j�́A�Ɨp���Y�i�V�x�n��L���،����̋��Z���Y�j������ꍇ�́A��������Ɖ��l�ɉ��������̂ł��B
�R�@�������l�́A��Ɖ��l���瑼�l���{�ł���L���q�������z���T���������̂ł��B
�@�@��Value Express�ł́A���Z����u�V�x�n�v�Ƃ�������Ȗڂ͑��݂��Ȃ����߁A��c�Ɨp���Y�Ƃ��čl�����Ă��܂���B�������u�����s���Y�v�͍l�����Ă��܂��B
�C�������i���{�R�X�g�j
�������́A�u���ԉ��l�v���l�����邽�߂ɗp����A�^�C�~���O�ƃ��X�N���v�邽�߂̎w�W�ł��i�����̂悤�Ȃ��̂ł��j�B��Ƃ������B����ɓ������ẮA�����ҁi���̏ꍇ�A����ƗL���q���̏o����j�ɑ��ĉ��炩�̃��^�[���i���Ԃ�j���K�v�ƂȂ�܂��B�ؓ��ɑ��闘���⊔���ɑ���z�������̑�\�ł��B�����҂ɑ��邱���������^�[���̃��[�g�i�x��������L���s�^���Q�C���A�z�������l���������́j���������i���{�R�X�g�A�v�����v���Ƃ��Ăт܂��j�ƌĂт܂��B
���{�R�X�g�́A�������B��ɂ��u�L���q���̏o����ɂ����́����R�X�g�v�Ɓu����ɂ����́����厑�{�R�X�g�v�ɑ�ʂ���邱�Ƃ���A�S�Ђ̎��{�R�X�g�́A���҂̃��[�g�̉��d���ς��Ƃ��ĎZ�o���邱�ƂɂȂ�܂��B������u���d���ώ��{�R�X�g�iWACC�j�v�ƌĂт܂��B
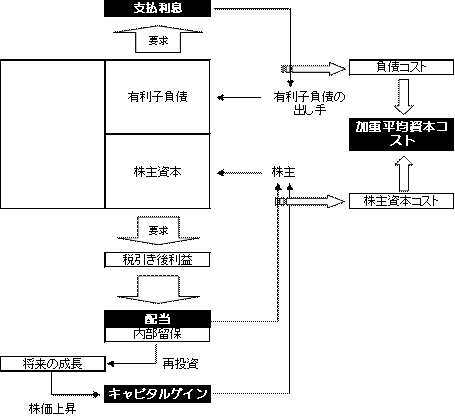 |
�D��Ɖ��l�̌���
�Ō�Ɋ�Ɖ��l�̌����ł����A�Ⴆ�Ό��Z��������ۂɁA�o�험�v�݂̂����Ă���悢�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�o�험�v�̎Z�o�ߒ��A���Ȃ킿������p�\���A�܂����萫�A�������Ƃ����ϓ_����o�����X�V�[�g�̓��e�ɂ����ӂ��K�v�ł��B�܂��A���Ђ̕��͂Ƒ��Ђ̕��͂ł͎��_���قȂ��Ă���A���Ђ̕��͂ł��ǂ̂悤�ȖړI�ŕ��͂���̂��A���肪�ڋq�Ȃ̂������̑ݏo��Ȃ̂��ɂ���Ď��_�͈قȂ�܂��B��Ȃ��Ƃ́A�����ړI��O���ɒu���Ȃ���S�̂����āA�|�C���g���������邱�ƂŁA��Ɖ��l�ɂ����l�̂��Ƃ������܂��B
��Ɖ��l�̏ꍇ�傫���́A�w�@���Ёi�q��Њ܂ށj�̉��l������܂��͊���̗���Ō��鑤�x�ƁA�w�A���Ђ̉��l�����鑤�x�Ƃŕ�����A����ɑ��Ђ̉��l�����鑤���ړI�ɂ��|�C���g�͈قȂ�܂��B
��{�I�ɂ́A�@�̏ꍇ�́A���Ƃ������Ɏ��v���グ�Ă��邩�A�ߏ�ȗL���q�����Ŋ������l���ʑ����Ă��Ȃ�������ȃ|�C���g�ƂȂ�܂��B
�A�̏ꍇ��ɁA�w�A-1�V�K���Ƃɐi�o����ۂɒ����I�ȖړI�Ŏ��Ƃ�����ꍇ�x�ƁA�w�A-2����Ƃ�A���Ɖ��l�͒Ⴂ���������Y�̑傫����Ƃ����A���̌�߂������ɔ��p�����v��ړI�̏ꍇ�x�ɕ�����܂��B
�A-1�̏ꍇ�A�@�Ɠ��l�Ŏ��Ɖ��l�⊔�����l���|�C���g�ɂ���ꍇ����������܂��B
�A-2�̏ꍇ�A���Ɖ��l���������A��c�Ɨp���Y�i�V�x�n����Z���Y�j���傫���ꍇ���|�C���g�ƂȂ邱�Ƃ���������܂��B��c�Ɨp���Y���������l�ƗL���q���̍��v�ł����Ɖ��l�������Ă���i���Ɖ��l���}�C�i�X�Ƃ������Ƃł��j�A������߁A�L���q����ԍς��Ă��玑�Y�p���Ă����v���o�邽�߁A�����ΏۂƂȂ�₷���Ȃ�܂��B
��Q&A
�EM&A�ł̊�Ɖ��l�]���i�ȉ��o�����G�[�V�����j�̈ʒu�Â�
�@�o�����G�[�V�����́A��{�I�ɍ������\����ɎZ�o���邱�Ƃ������ł����A����ł͔������Ȃ��_������܂��B��O�̎��Y�╉�A���[�K�����X�N�A�r�W�l�X���X�N���ł��B�����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA��Ɍ��F��v�m��ٌ�m�A�R���T���^���g�������{����̂��A�f���[�f���W�F���X�ł��B
�@M&A�ɂ����ăo�����G�[�V�����́A���̓�����Ŕ���i���p�j���i�̖ڈ������邽�߂Ɏ��{���邱�Ƃ������A�f���[�f���W�F���X�͍Ō�̒i�K�Ŕ�������Ƃɖ{���ɖ�肪�Ȃ������m�F���邽�߂Ɏ��{���邱�Ƃ���������܂��B
�EFCF�Ɖ�v���CF�̈Ⴂ
FCF�͎��Ƃ̐��ݏo����CF�Ƃ����Ӗ��ŁA��v���CF�́A���ݎ茳�ɂ���L���b�V���A�܂��͂����Ɋ����ł�����̂Ƃ����Ӗ��ł��B�Z�o�ߒ��Ŏ��Ă��镔��������܂����A�{���I�ɂ͈قȂ�܂��B
�EDCF�@�ɖ��`���Y�i�c�ƌ����j�̉��l��A�L���،���y�n���̎����͍l������Ă��邩�H
�@�܂��A���`���Y�̉��l�ł��邪�A���ړI�ɂ͍l������Ă��Ȃ����ԐړI�ɂ͍l������Ă��܂��BDCF�@�͊�Ƃ̏������v�ACF�̌��݉��l�����Ɖ��l�Ƃ����@�̂��߁AB/S�ɂ��閳�`���Y�̉��l�͒��ړI�ɂ͍l������Ă��܂���B���������`���Y�Ɏ��v�ނ����̉��l������ƍl����Ȃ�ADCF�@�͎��v����ɉ��l���Z�o���Ă����@�Ȃ̂ŁA�ԐړI�ɂ͍l�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���ɗL���،���y�n���̎����ł����A�l������ꍇ�����邵�A���Ȃ��ꍇ������܂��BDCF�@�ł͎��Ɖ��l�ɔ�c�Ɨp���Y�����Z�������̂���Ɖ��l�ł��邽�߁A��c�Ɨp���Y�ɗL���،���y�n������A���̎������Z�o�\�ł���A�l�����邱�Ƃ͂ł��܂��B�������A��c�Ɨp�ł͂Ȃ����Ɨp�ł���A���`���Y�Ɠ������߂��Ƃ邽�߁A���ړI�ɂ͍l���͂��ꂸ�A�ԐړI�ɍl�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
Value Express�ł͌��Z���̐��l�Ɋ�Â��Ă��邽�߁A���Z������ɂȂ�܂��B
Copyright 2006-2007 TEIKOKU DATABANK,LTD. all rights reserved